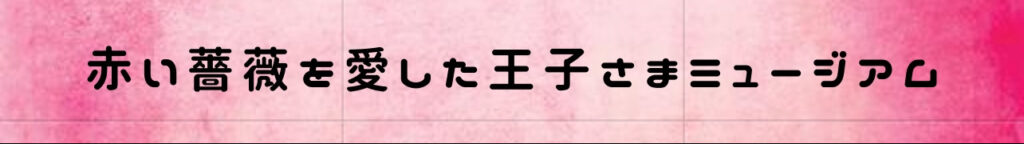あらすじ
synopsis

詳しいあらすじ
ある日、パイロットの「ぼく」を乗せた飛行機が故障して文明から遠く離れたサハラ砂漠に不時着してしまう。8日分の水しかなく、周囲1000マイル以内に誰もいないであろう孤独な砂漠で「ぼく」は不安な夜を過ごした。ここで、「ぼく」は思いがけず “星の王子さま “と呼ばれる少年と出会う。あざやかな金色の髪、愛くるしい笑い、そして答えが出るまで質問を繰り返す純粋さを持つ王子。
王子は「ぼく」に羊の絵を描くように頼む。「ぼく」はまず、蛇の中に象がいる絵を見せると、王子は驚いたことにそれを正しく解釈する。羊を描くのに3回失敗した後、苛立った「ぼく」は簡単な木箱を描き、その中に羊がいると主張する。すると王子は、これこそ自分が望んでいた絵だと言い放つ。
砂漠で8日間、「ぼく」が飛行機を修理している間、王子は自分の人生を語り続ける。王子の生まれた星は、地球でいえば「B612」と呼ばれる小惑星のようなもの。小惑星の最も顕著な特徴は、3つの極小火山(2つは活火山、1つは休火山)と様々な植物である。王子はその昔、火山を掃除し、この星の土壌にはびこる不要な種子や小枝を刈り取った。特に、地表を覆い尽くさんばかりのバオバブの木を引き抜いたという。バオバブの存在を認識した瞬間に根こそぎ取り除かなければ、その根は小さな惑星に壊滅的な影響を及ぼしかねない。そこで王子は、好ましくない植物を食べてくれる羊を欲しがるが、とげのあるバラも食べてしまうのではないかと心配になる。
王子は、小惑星にしばらく前に生え始めた、美しいが愚かなバラに恋をしていることを「ぼく」に話す。そのバラは見栄っ張りで、病気を大げさに言って注目させ、王子に世話を焼かせようとする。王子はバラに栄養を与え、寒さと風から守るために屏風とガラス球を作り、水をやり、毛虫を防いで一所懸命に世話をしたという。
王子はバラに恋をしたが、やがてバラに利用されていると感じるようになり、この星を出て宇宙を探検する決意をした。
別れの時、バラは「愛していることを伝えられなかった」と王子に謝る。初めて見るバラのしおらしい態度と弱さに驚く王子さま。王子は気持ちの整理がつかないまま旅に出る。バラと一緒にいるとき、バラの愛し方がわからなかった。バラのむなしい言葉を気にするのではなく、優しい行動に気づくべきだったと王子はあとで嘆く。
王子はその後、他の6つの惑星を訪れる。それぞれの惑星には、非合理的で狭量な大人が一人住んでいた。そこで出会うのは。
1. 臣下を持たず、日没時に太陽を沈めろというような、従えない命令ばかりして、自分の体面を保つことだけに必死な王様
2. 自分の住む惑星で最も称賛されることを望み、賞賛の言葉しか耳に入らない自惚れ屋
3.酒を飲むことを恥じ、それを忘れるために酒を飲む酔っぱらい
4. 夜空の星の美しさには気づかず、そのすべてを「所有」するために延々と星を毎日数え、星の所有権を主張するビジネスマン
5. 一日が1分しかないような小さな惑星の昼と夜に対応するために、30秒ごとにランプポストを消灯し、再点灯するという命令に盲目的に従うことで人生を浪費している点燈夫
6. どこにも行ったことがなく、記録したものを見たこともない年老いた地理学者
といった、どこかへんてこな大人ばかりだった。
この6番目の星にいた地理学者は、王子に自分のバラが記録されない儚い存在であることを告げ、次に7番目の星、地球を訪れることを勧める。
地球の砂漠に降り立った王子は、まずヘビに出会う。ヘビからは「人間と友だちになっても寂しいよ」と教わる。その後、王子は高い火山を見、数千本のバラの群生に出会う。自分の星を愛し、自分の小惑星の火山とバラの花を愛おしく、特別に思っていた王子は、自分の星のものよりずっと高い山、自分の星のバラよりずっとたくさんのバラを見つけて、自分の愛した小惑星、火山、バラはありふれた、つまらないものであったのかと思い、泣く。
泣いている王子のところに、キツネが現れる。悲しさを紛らわせるために遊んで欲しいと頼む王子に、仲良くならないと遊べない、とキツネは言う。キツネによれば、「仲良くなる」とは、あるものを他の同じようなものとは違う特別なものだと考えること、あるものに対して他よりもずっと時間をかけ、何かを見るにつけそれをいつも思い出すようになることだという。これを聞いた王子は、いくらほかにたくさんのバラがあっても、自分が美しいと思い精一杯の世話をしたバラはやはり愛おしく、自分にとって一番のバラなのだと悟る。 キツネと別れるときになり、王子は自分がキツネと「仲良く」なっていたことに気付く。別れの悲しさを前に「相手を悲しくさせるのなら、仲良くなんかならなければ良かった」と言う王子に、「黄色く色づく麦畑を見て、王子の美しい金髪を思い出せるなら、仲良くなったことは決して無駄なこと、悪いことではなかった」とキツネは答える。別れ際、王子は「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。たいせつなことは、 目に見えないってことだよ。」という「秘密」をキツネから教えられる。
日々飛行機を修理しようと悪戦苦闘するかたわら、こんな話を王子から聞いていた「ぼく」は、ついに蓄えの水が底をつき、途方に暮れる。
「井戸を探しに行こう」という王子に、砂漠の中で見つかるわけはないと思いながらついて行った「ぼく」は、本当に井戸を発見する。王子と一緒に水を飲みながら、「ぼく」は王子から、明日で王子が地球に来て1年になると教えられる。王子はその場に残り、「ぼく」は飛行機の修理をするために戻っていった。
翌日、奇跡的に飛行機が直り、「ぼく」は王子に知らせに行く。すると、王子はヘビと話をしていた。王子が砂漠にやってきたのは、1年前と星の配置が全く同じ時に、強い毒を持つヘビに噛まれることで、重たい体を置いて自分の小惑星に帰るためだったのだ。別れを悲しむ「ぼく」に、「自分は自分の星に帰るのだから、きみは夜空を見上げて、その星のどれかの上で、自分が笑っていると想像すれば良いんだ。そうすれば、君は星全部が笑っているように見えるはずだから」と語る。王子は「ぼく」が見守る中、ヘビに自ら噛まれて、砂漠に音もなく倒れた。
翌日、王子の身体は跡形もなくなっていた。王子が自分の星に帰れたのだと「ぼく」は考え、夜空を見上げる。王子が笑っているのだろうと考えるときには、夜空は笑顔で満ちているように見えるのだが、万一王子が悲しんでいたらと考えると、そのうちのひとつに王子がいるであろういくつもの星々がみな、涙でいっぱいになっているかのように、「ぼく」には見えるのであった。
物語は、王子と「ぼく」が出会った場所、そして蛇が王子をかんだ場所の風景を描いて終わる。 王子がバラの待つ生まれた星に帰国したのか、それとも死んでしまったのか、その判断は読者の気持ちに委ねられている。
(wikipediaより)